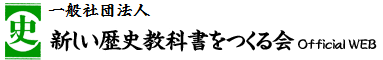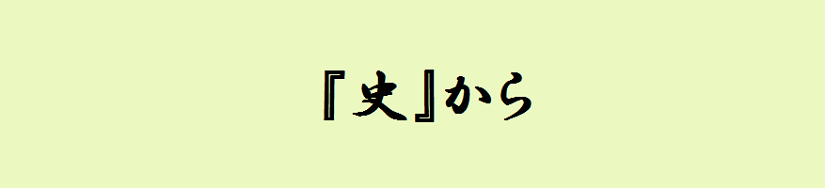明治維新の原動力となった崎門の國體思想
百五十年前の慶応三(一八六七)年十月十四日、徳川幕府第十五代将軍慶喜は、「従来之旧習を改め、政権を朝廷に帰し奉り」とする上表を朝廷に提出、翌十五日朝廷はそれを受け入れた。大政奉還である。同年十二月九日、朝廷は王政復古の大号令を発し、ついに明治維新の大業は成った。
明治維新の最も重要な意義は、「鎌倉幕府以来約七百年に及んだ幕府体制を倒し、天皇親政という本来の日本の姿に戻した」ということである。それは、五箇条の御誓文に際して、明治天皇から臣下が賜った維新の詔に明確に示されている。
明治維新百年を控えた昭和四十年、平泉澄門下の鳥巣通明は、維新史を矮小化しようとする一部の歴史家の中に「宮廷陰謀」論を説く者がいると指摘し、次のように述べていた。
「王政復古の大業をすなおに見て、それを安政以後の尊皇運動の積みかさねの結果として理解すれば、このような誤解曲解は一ぺんに消し飛んでしまうであろう」
明治維新を矮小化しようとする企ては、いまなお続いている。例えば、原田伊織氏は、〈薩摩・長州による軍事的クーデタを「明治維新」と呼ぶならば、「明治維新」という過ちを犯したことがその後の国家運営を誤り…〉と書いている。もちろん、明治維新には権力闘争の側面も外国勢力の関与もあった。しかし、明治維新の意義は、まず天皇親政という國體の観点から考える必要がある。
筆者は、そうした思いも込め、拙著『GHQが恐れた崎門学 明治維新を導いた國體思想とは何か』(展転社)を上梓し、わざわざ補論を加えて、原田氏を厳しく批判した。
武家政権の前にも、藤原氏の摂関政治によって天皇親政の理想は損なわれていた。これに対して、醍醐天皇、村上天皇の延喜・天暦の御代のみならず、後三条天皇による延久の善政などが実現した。そして、承久三(一二二一)年五月、延喜・天暦の御代の再現を目指された後鳥羽上皇は、執権北条義時追討の院宣を出し、承久の変を起こされた。
ところが、鎌倉幕府によって鎮圧され、後鳥羽上皇は隠岐島へ、順徳上皇は佐渡島へ配流され、土御門上皇も自ら土佐国へ配流された。三上皇は絶海の孤島にわびしくお過しになった。
この承久の悲劇を乗り越え、後醍醐天皇は元弘三(一三三三)年、ついに鎌倉幕府を倒し、建武の新政を開始されたが、足利尊氏の裏切りによって二年半で新政は崩壊に追い込まれた。
しかし、この悲劇の陰で、「七たび人間に生まれて、もって国賊を滅ぼさん」と言い残した楠正成(大楠公)の誠忠と、後醍醐天皇崩御に直面し、幼少の後村上天皇に献上すべく北畠親房が著した『神皇正統記』が、不滅の精神として遺された。
やがてその精神は徳川幕府全盛時代に蘇り、明暦三 (一六五七)年に水戸光圀(義公)が『大日本史』編纂を開始、また、ほぼ同時期に山崎闇斎によって崎門・垂加の学が樹立された。水戸学と崎門学が重視したのは、南朝の殉忠の精神であった。
そして、天皇親政という日本の本来の姿についての揺るぎない確信、理想の回復を試み志半ばで斃れた先覚者たちへの深い敬慕、先覚者の魂を継がんとする自覚と実践において、崎門学は中心的役割を担っていく。
朝権回復を目指した崎門派の行動が明治維新の百年以上前から開始されていたことに注目すべきである。崎門学を学んだ竹内式部は、桃園天皇の近習である徳大寺公城らに講義を開始し、宝暦六(一七五六)年には、公城による桃園天皇への直接進講が実現した。
ところが、朝権回復の思想の拡大を警戒する徳川幕府によって式部は京都から追放された(宝暦事件)。明和四(一七六七)年には、『柳子新論』を書き、尊皇思想を唱えた山県大弐が処刑された(明和事件)。
これらの挫折を乗り越え、朝権回復運動に挺身した高山彦九郎もまた寛政五(一七九三)年に自決に追い込まれ、その三年後には盟友唐崎常陸介も彦九郎の後を追った。
やがて幕末には、安政の大獄で梅田雲浜が尊い犠牲になった。彦九郎、常陸介、雲浜いずれも崎門に連なる志士であった。まさに崎門派は「百難屈せず、先師倒れて後生之をつぎ」(平泉澄)という言葉通り、先人の無念に心を寄せ、自ら尊皇の大義に殉じたのである。
崎門に連なる志士たちは、闇斎の高弟浅見絅斎の『靖献遺言』に収められた「節に死した男たち」と大楠公の精神とを重ね合わせ、自らの魂を鼓舞してやまなかった。
絅斎の高弟若林強斎は、「臣下の道は楠公の外になし」とし、書斎を望楠と号した。『靖献遺言』と並び称される『日本外史』を著して頼山陽の尊皇論にも、崎門の学風は流れていた。
大政奉還百五十周年を迎えるいまこそ、明治維新の本義を正しく理解するとともに、その原動力となった崎門の思想と行動の不朽の価値に光を当てるときなのではなかろうか。
平成29年11月9日更新